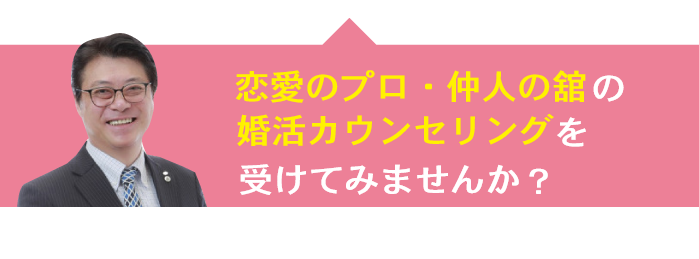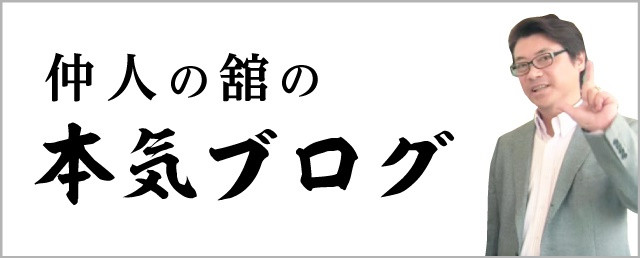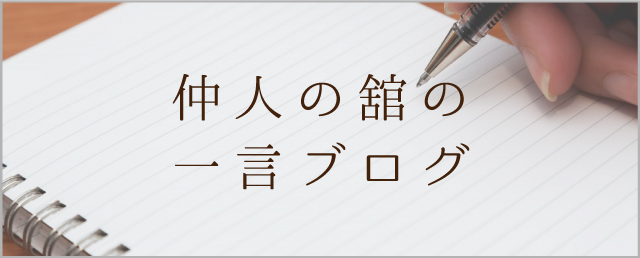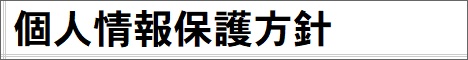はじめに
恋愛のプロ・仲人の舘です。
結婚相談所は「現代の婚活サービス」として語られることが多いですが、その成り立ちを辿ると戦後からの日本社会の変化と深く結びついています。
今回は、戦後の復興期から現在に至るまでの結婚相談所の歴史を振り返りながら、婚活の在り方がどのように進化してきたのかを解説していきます。
戦後復興期と「仲人文化」の始まり
戦後直後、日本は急速な社会再建期にありました。
生活基盤を整えることが最優先で、結婚は「家同士の結びつき」として重要な意味を持っていました。
当時は親族や地域社会の紹介による結婚が主流で、仲人は家族の延長線上にある存在でした。
結婚相談所と呼べる仕組みはまだ存在せず、地域や親戚のネットワークがその役割を果たしていたのです。
高度経済成長期と結婚相談所の誕生
1960年代から70年代にかけて、高度経済成長とともに都市化が進みました。
地方から都市に移り住む若者が増え、従来の「親戚や地域のつながり」に頼った縁結びが難しくなります。
この時期、初めて「結婚相談所」と呼ばれる形態が誕生しました。
仲人が職業として縁組みをサポートし、プロフィールカードや写真を使ったマッチングの基盤が整ったのもこの頃です。
1980〜90年代:情報化とサービスの多様化
バブル期を経て、結婚観にも大きな変化が訪れます。
恋愛結婚が主流となりつつも「出会いの機会が少ない」という課題は残りました。
そのニーズを背景に、結婚相談所はより組織化され、全国規模の連盟が形成されるようになります。
仲人は単なる紹介役ではなく、会員の希望条件を整理し、双方の意向を尊重するコーディネーターとしての役割を担い始めました。
2000年代:インターネット時代の到来
インターネットの普及により、出会いの場は大きく変化しました。
婚活サイトやマッチングアプリが台頭し、結婚相談所もデータベースやオンライン検索システムを導入。
プロフィール検索によって条件に合った相手を効率的に探せるようになり、成婚までのプロセスもスピード化していきました。
しかし同時に「機械的な出会い」という懸念も生まれ、改めて仲人の存在価値が見直され始めます。
現代:仲人の役割の再定義
現在の結婚相談所は、データと人のサポートを融合させた形へ進化しています。
条件検索だけでは測れない「人柄」「価値観の相性」を、仲人が客観的に見極めることが求められています。
特に30代〜40代の女性にとっては、効率と同時に「信頼できる助言者」が必要不可欠であり、ここに仲人の専門性が生かされています。
結婚相談所の歴史から学べること
結婚相談所は時代の変化に合わせて形を変えてきましたが、本質は変わっていません。
それは「人と人をつなぎ、幸せな家庭を築くきっかけを提供する」という役割です。
戦後の仲人文化から現代のデジタル婚活までを振り返ると、出会いの方法が進化しても、人が人を支える価値は普遍的であることがわかります。
まとめ
結婚相談所の歴史を辿ると、日本社会そのものの変化が浮かび上がってきます。
都市化、情報化、デジタル化といった流れの中で、結婚相談所は常に「時代に合った縁結び」を提供してきました。そして今、最も求められているのは「人が人を見てサポートする力」です。
結婚は人生の大きな選択であり、そのサポートに仲人が果たす役割はこれからも揺らぐことはないでしょう。

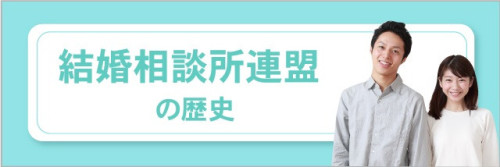
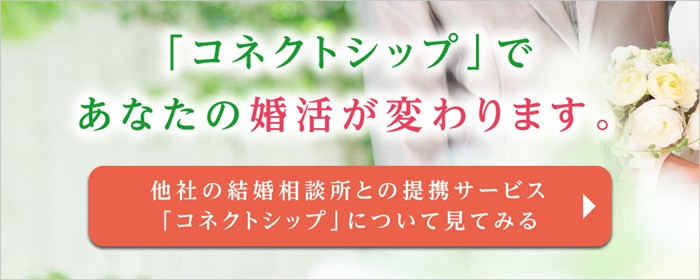
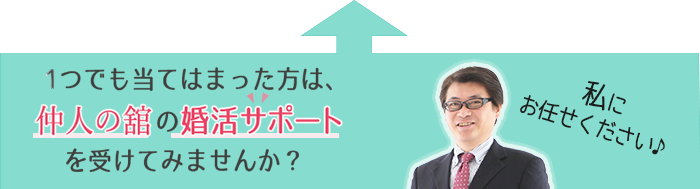
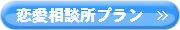


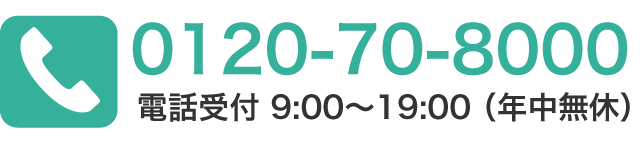



 恋愛のプロ・仲人の舘は、口が上手いわけでも、押しが強いわけでも、まして魔法を使えるわけでもありません。
恋愛のプロ・仲人の舘は、口が上手いわけでも、押しが強いわけでも、まして魔法を使えるわけでもありません。