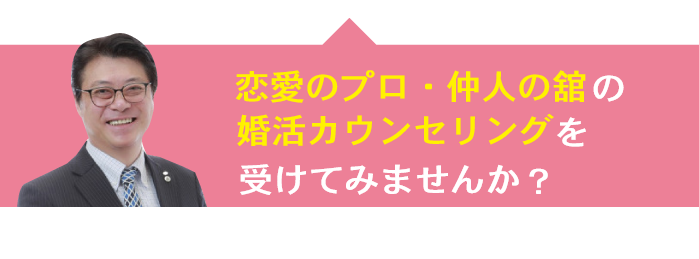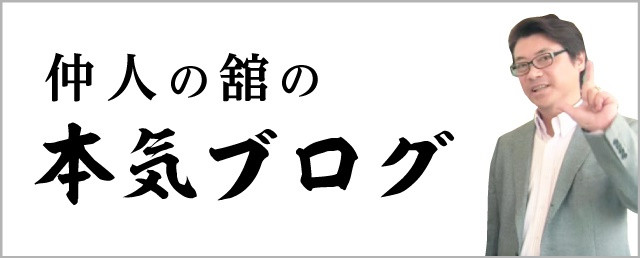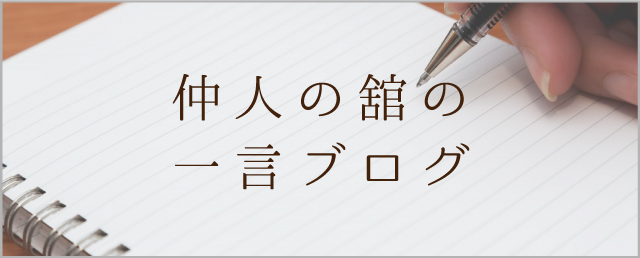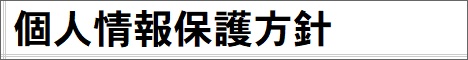はじめに
恋愛のプロ・仲人の舘です。
結婚相談所は現代の婚活サービスとして認知されていますが、その背景には日本独自の「仲人文化」の歴史があります。
今回は、仲人制度の原点を振り返りながら、結婚相談所がどのように発展してきたのかを専門的な視点から解説します。
仲人文化の始まり
仲人の存在は江戸時代にまで遡ります。
当時の結婚は「家と家の結びつき」が中心で、当人同士の意思よりも家族や地域社会の意向が重視されていました。
仲人は信頼のおける第三者として両家を取り持ち、結婚生活が安定するよう橋渡し役を担いました。
この「信頼の媒介者」という役割が、現代の結婚相談所に受け継がれています。
戦後社会と結婚相談所の誕生
戦後の復興期には都市化が進み、親族や地域の紹介に頼ることが難しくなりました。
ここで初めて「結婚相談所」という仕組みが生まれ、仲人が職業的に縁組みをサポートする形が整います。
当時は紙のプロフィールカードや写真を用いてお見合いが行われ、現代のマッチングシステムの原型となりました。
高度経済成長期の変化
1960年代以降、経済成長とともに結婚観も多様化しました。
恋愛結婚が増加した一方で、仕事に追われる若者が出会いの機会を失うケースも増えました。
結婚相談所はそうしたニーズに応える存在として広がり、仲人は「条件整理」と「相性の見極め」を兼ねる専門家へと役割を拡大しました。
現代における仲人の役割
現在ではインターネットやアプリを通じた婚活も一般的になりましたが、効率性と引き換えに「信頼できる相手かどうか」「人柄や価値観が合うか」という点が見えにくくなっています。
ここで再び重要視されるのが仲人の目利き力です。
経験に基づいたアドバイスや、第三者だからこそ気づける相性の指摘は、30代・40代の女性にとって大きな安心材料となります。
仲人制度の原点から学べること
仲人制度の歴史を振り返ると、形は変わっても「人と人を結びつける信頼の橋渡し」という本質は変わっていません。
テクノロジーが進化しても、最後に人を支えるのはやはり人です。
仲人は、結婚に対する真剣な思いを尊重し、成婚に向けて伴走する存在として、これからも欠かせない役割を果たし続けるでしょう。
まとめ
結婚相談所の歴史は、日本社会そのものの変遷と重なります。
仲人制度の原点を知ることで、現代の婚活において「人の力」を見直すきっかけとなります。
結婚は人生の大きな選択です。その一歩を確かなものにするために、仲人という存在があなたを支えるのです。

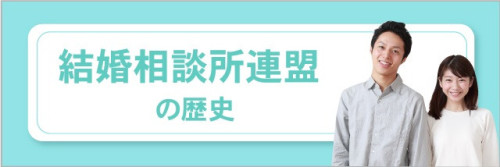
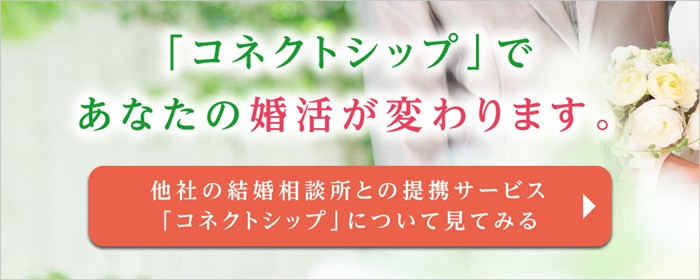
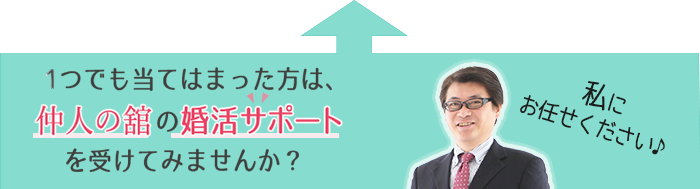
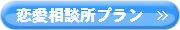


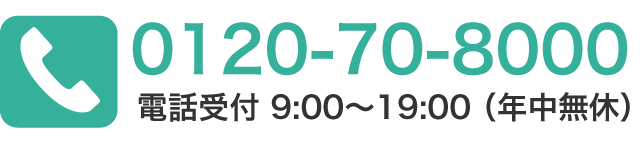



 恋愛のプロ・仲人の舘は、口が上手いわけでも、押しが強いわけでも、まして魔法を使えるわけでもありません。
恋愛のプロ・仲人の舘は、口が上手いわけでも、押しが強いわけでも、まして魔法を使えるわけでもありません。