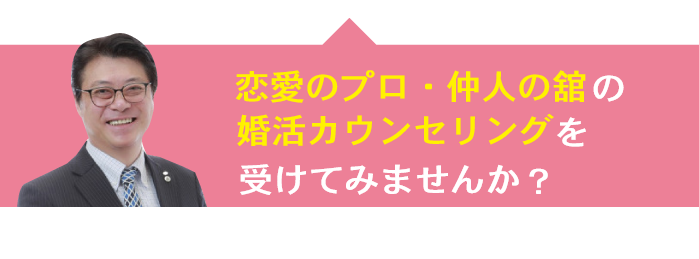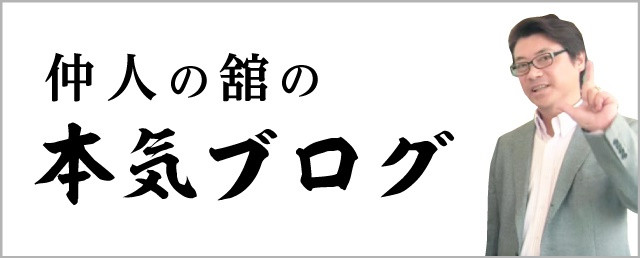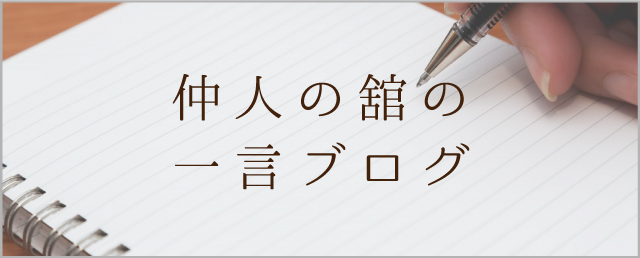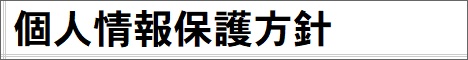はじめに
恋愛のプロ・仲人の舘です。
結婚相談所という存在は、戦後から現代まで、時代の変化に合わせて姿を変えてきました。
その歩みを知ることで、今の婚活における成功の秘訣が見えてきます。
本記事では、仲人の立場から「時代ごとの成婚の形」と「成功法則」を掘り下げて解説していきます。
昭和の結婚相談所 ― 紹介中心の縁結び
戦後から昭和にかけては、地域社会や親戚を通じた「紹介」が結婚の主流でした。
結婚相談所もその延長線上にあり、仲人が家族ぐるみで相手を見極めるのが一般的でした。
この時代の成功法則は「家と家の相性」。
本人同士の意思よりも、両家の価値観の一致が重視されていました。
平成初期 ― 条件重視の婚活時代
バブル崩壊後、経済的な不安が広がり、「安定」を求める傾向が強まりました。
平成初期の結婚相談所では、学歴や職業、年収などの条件を軸にしたマッチングが主流になりました。
いわば「条件の最適化」が成功の鍵であり、結婚は個人の選択でありながら、経済的安定が大きなウエイトを占めていたのです。
平成後期 ― 自己実現と相性重視の融合
インターネットが普及し、価値観の多様化が進むと、結婚に対する考え方も変わってきました。
「条件」だけでなく、「一緒にいて心地よいか」「価値観が合うか」という要素が重要視されるようになります。
この時代の成功法則は「条件と感性のバランス」。
結婚相談所はデータと対面の両方を駆使し、出会いの幅を広げていきました。
令和 ― データ活用と仲人の役割強化
令和の現在、AIやデータ分析が婚活の現場に導入されています。
アプリやマッチングサービスも普及しましたが、結婚相談所は「データ+人の目」で差別化を図っています。
プロフィールだけでは分からない「人柄」や「将来設計」を仲人が引き出し、交際から成婚へとつなげていきます。
この時代の成功法則は「効率と人間力の融合」です。
仲人が見てきた成婚の共通点
時代ごとに婚活の形は変わってきましたが、成婚に至る方には共通点があります。
- 自分の希望を明確にしつつ柔軟に調整できること
- 相手に求める条件と、自分が提供できる価値のバランスを理解していること
- 仲人のアドバイスを取り入れ、軌道修正を恐れないこと
これらは昭和から令和まで、普遍的な「成婚の法則」です。
まとめ
結婚相談所の歴史を振り返ると、成婚の形は時代に応じて変化してきました。
しかし根底にあるのは、仲人が「人と人をつなぐ」役割を果たしてきたことです。
30代・40代の皆さまにとって、今の婚活で大切なのは「効率的に出会いを広げつつ、人間的な相性を見極める」こと。
その両立を支援できるのが結婚相談所であり、仲人の専門性が求められる理由なのです。

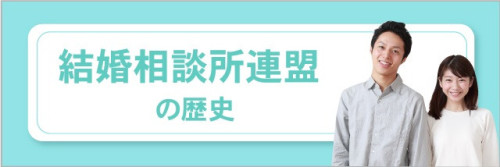
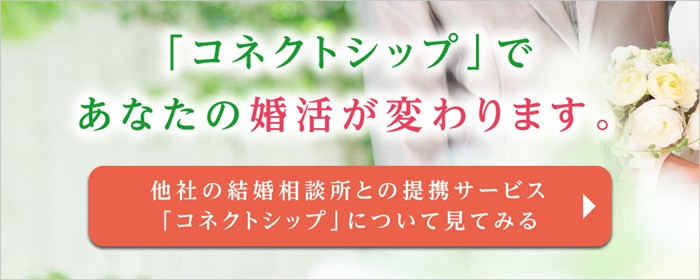
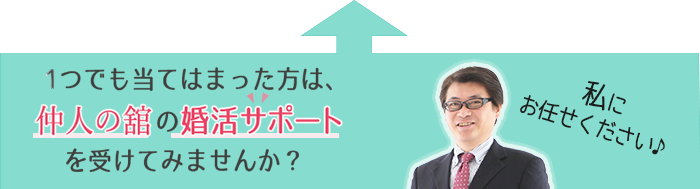
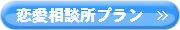


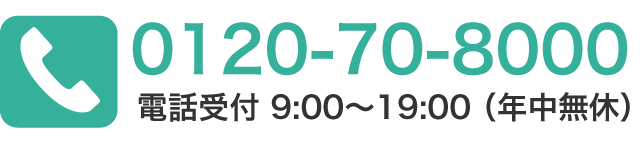



 恋愛のプロ・仲人の舘は、口が上手いわけでも、押しが強いわけでも、まして魔法を使えるわけでもありません。
恋愛のプロ・仲人の舘は、口が上手いわけでも、押しが強いわけでも、まして魔法を使えるわけでもありません。